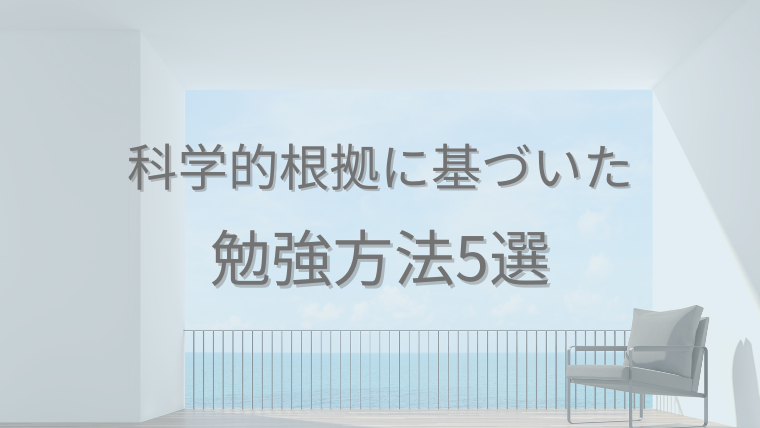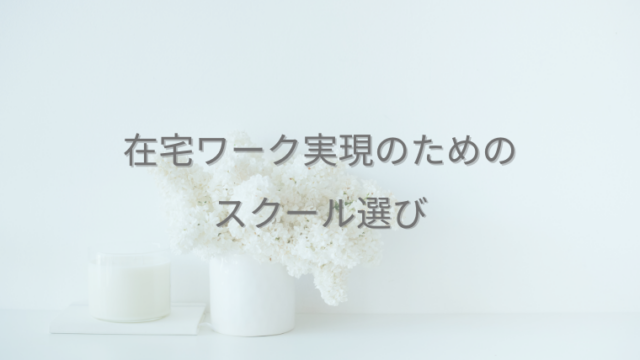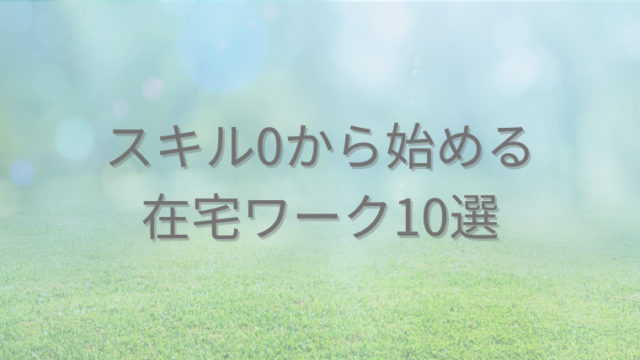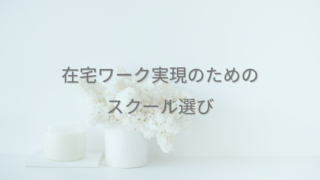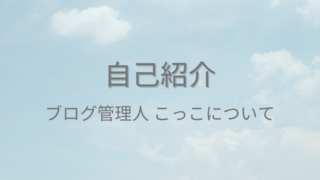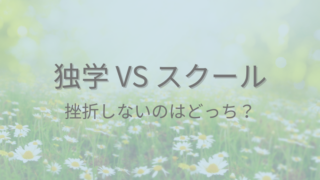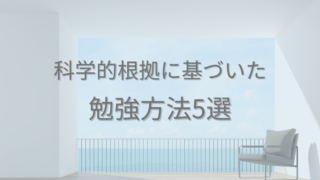◆ 仕事・家事・子育てに忙し過ぎてまとまった学習時間が取れない
◆ 勉強がなかなか進まなくて、気持ちだけ焦る
◆ そもそも効率のいい勉強方法が分からない
こんなお悩みありませんか?
今回の記事では、忙しいあなたにこそ活用して欲しい科学的根拠に基づいた
「効率的な勉強方法」についてお伝えします。
私自身、要領がいい方ではないので「効率的に」は常に意識しているのですが、
なかなか出来ていないのが現状です。
「在宅ワークを始めたい」と思ってスクールで勉強を始めるも、見た動画をとりあえず
ノートにまとめるという「効率的」とは真逆のことをしていました。
そして1ヶ月後「このままだと、インプットだけで一生終わってしまう。
勉強方法を変えなくては・・・」と焦りはじめたのです。
ガッツリ偏差値教育で育ったミドル40’sは、「勉強=暗記=とりあえずノートに
まとめてみる」が自然と身に付いていました。(40代暗記力、破滅的なのに)
今回は「今の勉強方法だと時間をかけている割にあまり記憶に残っていない」
「子育てに忙しくてまとまった学習時間がとれない」と思っている方におすすめの
「科学的根拠に基づいた効率的な勉強方法」を5つピックアップしてみましたよ。
合わせて「実は効果の低い学習方法2選」もご紹介するので、
ぜひ参考にしてみてください。目からウロコ間違いないです。
【効果倍増】超効率的な学習方法の組み合わせ:
アクティブ・リコール+スペースドリピティション(感覚反復)
 いきなりですが、効果倍増が期待できる最強の勉強方法の組み合わせを紹介します。
いきなりですが、効果倍増が期待できる最強の勉強方法の組み合わせを紹介します。
その学習方法は、アクティブ・リコール+スペースド・リピティション(感覚反復)です。
簡単に言うと、少し時間を空けて繰り返し復習する方法です。
ご存じの通り、記憶は時間が経つほど薄れていきますが「忘れかけたタイミング」で
思い出すことで、記憶に残ります。
① インプットする(教科書・参考書を読む)
② アウトプットする(白紙に書き出す)
③ 翌日・数日後にもう一度思い出す
学習方法もシンプルなので、直ぐにでも試してみることができるのではないでしょうか?
次の章では、今紹介した「アクティブ・リコール」、「スペースド・リピティション」を
含む「効率的な勉強方法5選」を1つずつ解説していきますね。
科学的根拠に基づいた「効率的な勉強方法5選」
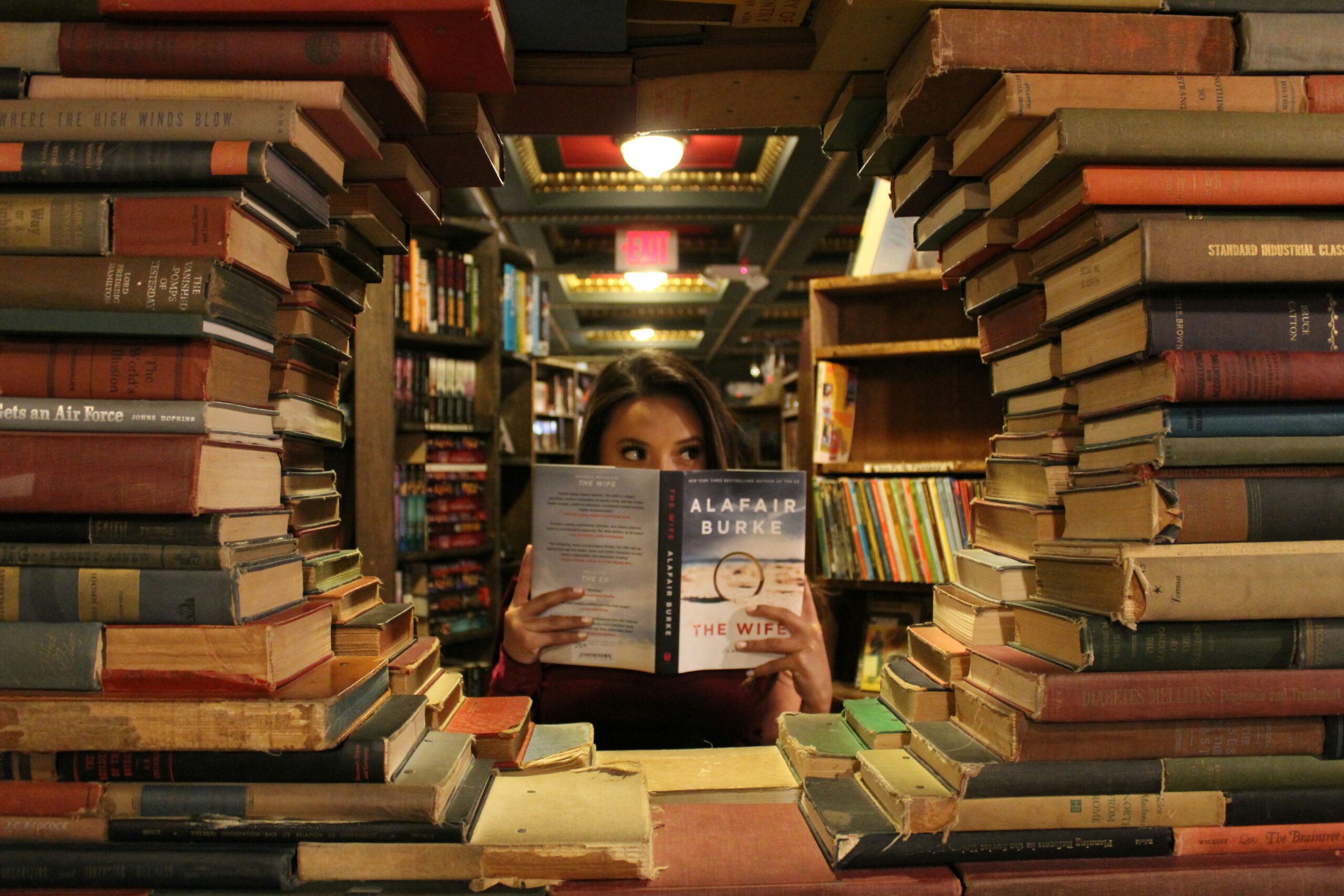 色々な勉強方法がありますが、せっかくなら効率よく、そして科学的にも学習効果が
色々な勉強方法がありますが、せっかくなら効率よく、そして科学的にも学習効果が
認められた方法でサクサク進めたいですよね。
最新の研究では、インプットよりもアウトプウトを重視した勉強方法が効率的
という結果が出ています。
しかしアウトプットの方法もさまざまです。
ただやみくもにしていても、それは無意味なこと。
そこで早速、科学的根拠に基づいた効果的な勉強方法を5つお伝えします。
① 分散学習(スペースド・リピティション)
分散学習は、学習の内容を間をあけて繰り返し学習する方法です。
まとめて勉強する一夜漬けより、記憶できる期間がかなり長くなると研究報告が
でています。
通勤中などのちょっとした時間にできるので、毎日少しづつ学習し、前回学習した内容を
思い出しながらすることで記憶が定着しやすくなります。
幅広い年齢・どの科目にも有効です。
語学や資格勉強などの暗記学習には、フラッシュカードやアプリを使って毎日少しずつ見直すことが大切です。
例:「今日は昨日覚えた単語を10分で復習」「次の日は、前々日と前日の
内容をまとめて復習」と言ったように感覚を少しずつ伸ばしていくと
効果的。
② アクティブ・リコール/テスト形式学習(練習テスト)
アクティブ・リコール、テスト形式学習は、学習内容を自分で思い出したりテスト形式で
復習する方法です。
覚えたことを口に出したり、問題集で解き直すことで記憶の定着率が上がります。
白紙を用意します。
そして教科書や参考書の1段落を読んだら閉じて、白紙に覚えた内容を
思い出して書いていきます。
(ノートとして残す必要はないので殴り書きでOK)
書きながら声に出したり、家族や友人に説明しているつもりで話すと
さらに効果アップです。
自分にクイズを出したり、スマホアプリのクイズやオーディオ問題を
するのもありですよ。
インプットしたことを自分の頭で思い出したり、アウトプットすることで
記憶の定着が一気に高まります。
【実体験】
宅地建物取引士の資格を取得する際に「スマホアプリの問題を解く」ことを
毎日10分間、取り入れて勉強していました。
まだ上の子が2歳の手のかかる時期。時短勤務ではありましたが
ワンオペだったので、とにかく勉強時間の確保が課題でした。
「保育園にお迎えに行く前に10分」と決めて、ランダムに出てくる
アプリの問題を解きまくっていました。(おかげで無事合格できました)
③ ポモドーロ法(短時間学習+休憩サイクル)
ポモドーロ法は、名前を効いたことがある方もいるのではないでしょうか?
「25分学習+5分休憩」といったように、短時間の学習と休憩を繰り返して行う
時間管理法です。
最近の研究では、計画的な休憩を先に決めておくと集中力のアップや気持ちの面でメリットが大きいことが分かっています。
自分の判断で休憩するよりも、一定間隔で休憩を入れる方が疲労感や集中力の低下を
抑えられ、より多くのタスクを達成できたという結果がでています。
休憩時間は、水分補給やストレッチなどリラックスタイムに。ついついスマホや
メールをチェックしがちですが、次の25分に再度集中するためにしっかり
休憩しましょう。
絶対に25分である必要はないので、「短サイクル学習」を家事の合間に
取り入れるのもおすすめです。
掃除の後に10分暗記を復習する、ちょっとできた隙間時間20分間に本を読むなど、
短い時間でもぜひ有効に使ってみてください。
25分間(または15〜20分)集中して勉強し、
その後5分程度の短い休憩を取るサイクルを繰り返します。
タイマーを使って時間管理すると継続しやすいですよ。
「毎回タイマーで計るのがめんどう」という人は、YouTubeで
「ポモドーロタイマー」と検索するのがおすすめ。
「25分+5分x〇セット」とポモドーロタイムがセットされており、
YouTubeを流しておくだけで2~3時間の時間管理をしてくれるチャンネルが
いくつもあります。
しかも集中力を高めてくれる528Hzの周波数が入った音や音楽、
他にも波やせせらぎ、ピアノなど色々なバージョンがあり、
気分によって変えていくのも楽しいかもしれませんね。
528Hzとは?
ソルフェジオ周波数の中の1つで、「奇跡の周波数」や「愛の周波数」と呼ばれる周波数です。DNA修復や細胞再生を促進し、心と体を癒す力があると言われています。
順天堂大学大学院医学研究科による「Effect of 528 Hz Music on the Endocrine System and Autonomic Nervous System」という論文の中でも「他の周波数の音楽よりも内分泌系や自律神経に良い影響をもたらし、5分間聞くだけで強いストレスを軽減する効果がある」と発表されています。
参照:ソルフェジオ周波数の科学的根拠はある!種類ごとの効果を解説
Effect of 528 Hz Music on the Endocrine System and Autonomic Nervous System
【実体験】
ポモドーロ法は、私の周りでも「効果あり!」の声をよく聞きます。
私自身も先程紹介したYouTubeを流して実践していますが、心地よい音が
気持ちを落ち着かせてくれて、集中して目の前のことに没頭できる実感があります。
この方法を取り入れたことで、これまでより長時間、集中して仕事が進められるようになりました。音楽が心地いいのに、なぜか夜活中にコックリすることがなくなりましたよ。
ぜひ試してみてください。
④ インタリービング学習(交互学習)
インタリービング学習とは、違う科目や内容を交互に学ぶ方法です。
英単語だけを覚える、数学の問題を解くといったように時間を区切って
勉強するのではなく、複数のことを組み合わせて学びます。
この方法によって脳が「切り替え」をしなければいけないので、それぞれの内容を
区別して覚える力が鍛えられます。
まとまった時間が取れない人でも、10分や20分など短い時間にいくつかの
学習内容を組み合わせることで、集中力も途切れにくいです。
1日目は英語→数学→英語、2日目は数学→英語→数学
など、違う科目や内容を組み合わせた勉強をおこなってみましょう。
フラッシュカードを使う場合でも、国語・英語・数学の問題を
混ぜて解くのがおすすめです。
はじめはなかなか脳の切り替えが上手く出来ず、難しく感じるかもしれませんが、
慣れると集中力が継続できるようになりますよ。
また短い時間に複数の内容に取り組むので、学習の飽き防止にもつながります。
【実体験】
私も仕事でよく活用します。長時間同じことを続けていると、飽きてくる、
集中力がなくなってくるのでポモドーロ法の25分ごとに仕事内容を変えたり、
合間に家事を挟んだりしています。
違う内容なので飽きがこず、集中力も持続し、ケアレスミスが減りました。
⑤ 自己説明・教える学習
自己説明や教える学習は、学習した内容を自分の言葉で説明したり、人に教えたりすることです。記憶の定着と学習内容の理解力を深める効果があります。
忙しい人は、「5分以内に誰かに説明するつもり」で
声に出して要点を言ってみたり、ポイントだけをノートやスマホに書き出す
だけでもOKです。
おまけ:実は効果の低い学習方法2選

私はこの事実を知って正直びっくりしました。
どちらも小学生の頃から今まで、何の疑問もなく当たり前のようにやっていた
学習方法だったからです。しかも科学的に「効果が低い」と分かっているのだそう。
教科書を何度も繰り返し読む(再読)
1回より2回読んだ方が少し効果はありますが、それ以上は大きな期待ができません。
今後は「読んでも2回まで」がおすすめです。
蛍光ペンでハイライトする
これはかなりの方が実践しているのではないでしょうか。もちろん私も当たり前でやっていました。
「教科書や参考書を読みながら、ハイライトをしていくこと」が勉強の取り掛かり
といっても過言ではありません。
学校でも先生から「今からいうところは大事だから線引いて~」と言われてましたよね。
でも実際はただ「やった気になるだけ」で、テスト結果にはほとんど差がないことが
多くの研究で分かっています。
まとめ
いかがだったでしょうか。
最新の研究結果では「読む=インプット」だけでは記憶が定着しにくく、自分の頭で考えてアウトプットすることが効率的な学習方法と結果が出ているようです。
毎日やることがたくさんあって忙しいので、なかなかゆっくり学習時間を
確保するのは難しいと思います。
ぜひ今日ご紹介した科学的根拠に基づいた学習方法を実践し、あなたに合った
効率的な方法を見つけてくださいね。
最後まで読んでいただきありがとうございました。
こっこ